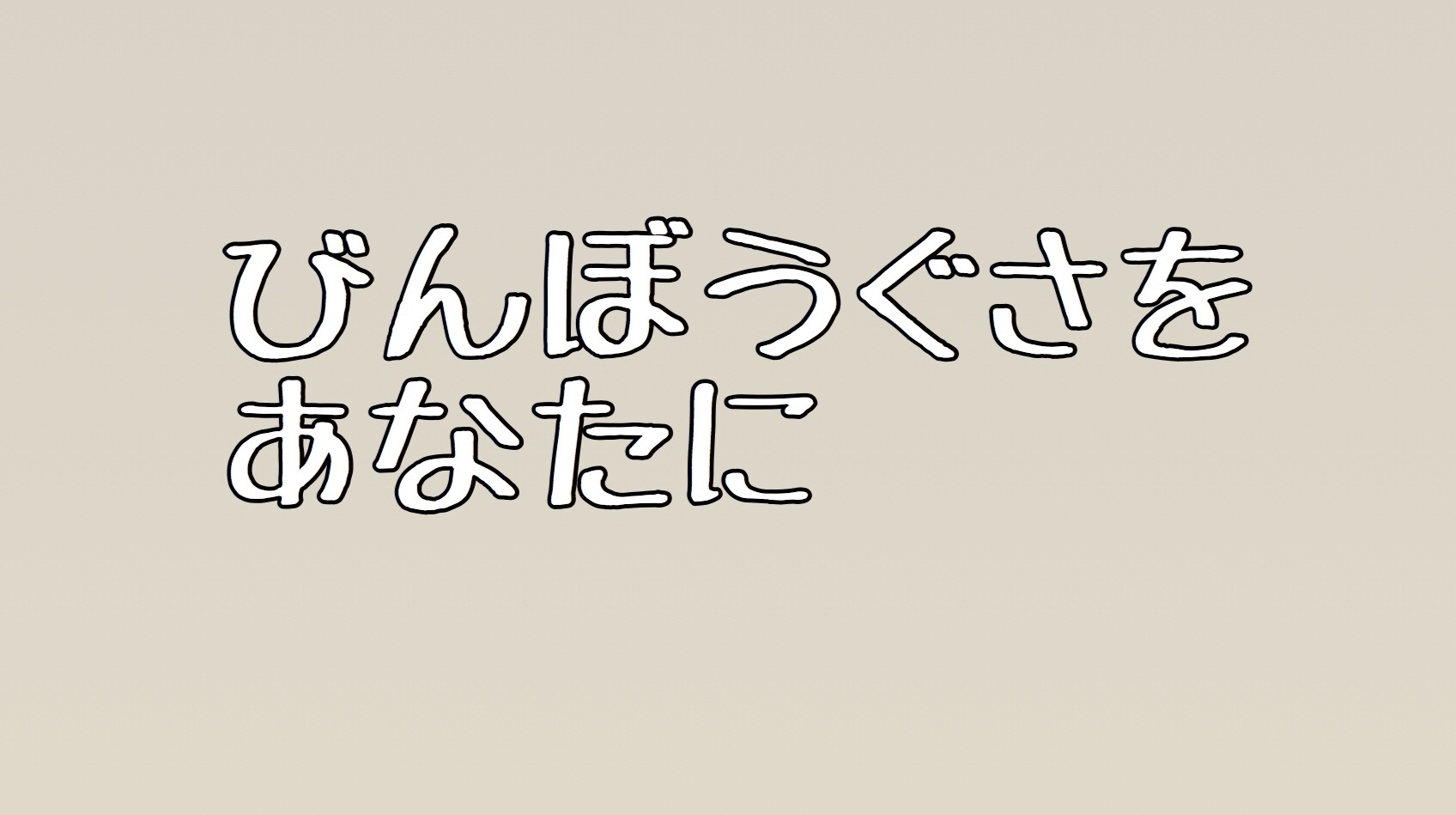「ゆぴちゃん」という女の子がいた。正確にはそれは私がそう呼んでいただけで、本当の名前は違うかもしれない。なぜなら、私が名前を訊き、たまたま聞き取った名前が「ゆぴちゃん」だったからだ。そう呼べば彼女は振り向いたから、二人の間の呼称として成立していたのだと思う。
新生活へ
30年以上前の話だ。私は小学生の頃、一度だけ引っ越しをしたことがある。小学校の頃の引っ越しは、何を差し置いても一大イベントである。ある日私は住み慣れたマンションに別れを告げ、4人家族にしてはやや広すぎる一軒家へ越した。慣れない土地、見知らぬ人。ソワソワする気持ちと、これからはじまる新生活に胸を躍らせていた記憶がある。
私は、学校にも土地にもすぐに馴染めるだろう…そんな風に思っていたが、なかなかにして難しかった。そもそも、転校生は転校生というラベルがあり、それを剥がすのは時間がかかるということを、当事者になるまで認識していなかったのだった。
したがって、しばらくの間登下校は一人だった。なんとなく、その土地の事や近所の顔ぶれを意識し始めたころ、毎日同じ時間に同じ場所に立っている小さな女の子を発見した。いや、彼女はずっといたのかもしれない。私が見つけるのに時間がかかっただけで。
最初は通り過ぎるだけだった。しかし、毎日の事だから、意識しないわけにはいかなかった。母親にそれとなく彼女のことを訊いてみたが、「そんな子と関わらないほうがいいわよ」と冷たく告げられた。
ある日、彼女はびんぼうぐさを持って立っていた。私のほうをチラッと見て、駆け寄って、その手に持ったびんぼうぐさを私に手渡そうとしたのだ。一瞬びっくりしたが、反射的に ~いや、反射的ではなく確実に意識的に~ 私はびんぼうぐさを受け取った。しかし、お互い無言だった。ただ、『彼女の手から私の手にびんぼうぐさが移動した』と形容しても差し支えないくらいの出来事だった。
びんぼうぐさをあなたに
ところで、びんぼうぐさという花を知っているだろうか。正式名称はハルジオンというらしいが、子どものころからそう呼ばれていること以外に知識はない。そう、もう一つあるとしたら、それはその名前のように『手にした人は貧乏になる』という迷信めいたものがある花だった。
びんぼうぐさは、いたるところで生えていた。幼いころ、私はなぜかその花が好きだった。その花の意味も知らなかったという理由も手伝って、どの花と比べても可愛い花だと思っていた。
そんな背景もあり、私は密かに憧れていた近所のお姉さんに、びんぼうぐさを摘んでプレゼントをしたこともあった。しかし、そのお姉さんの反応は私の期待を大きく裏切るものだった。
『これ、びんぼうぐさだよ。こんなのいらない!』
子どもは残酷だ。私も幼い子どもだったが、当時『お姉さん』と私が認識していた人もまた子どもだったのだろう。私が差し出したびんぼうぐさを汚いものでも触るように奪い取り、コンクリートの地面に放り投げたのだった。
私は泣きそうになりそうになりながら、必死で笑顔を振りまいた。好きなものを乱暴に扱われた怒りより、その場の空気を読むことのほうが先決と思えたからだ。
(このはなは、あげてはいなけなかったんだ)
幼い私は、瞬時にそう理解した。
「うん、きたないはなだね」
私はそう言った。心にもない言葉だった。
(ひとりになりたくない)
そんな恐怖心にも似た気持ちがあったのだと思う。
そして、この出来事は、今後長い間にわたって私の事を苦しめる出来事となる。誰かの感情を先読みすること、そしてそれにどうすれば沿うことができるか瞬時に判断すること。そのためには、いとも簡単に大事な誰かの事を傷つけられること。
話を戻そう。
引っ越しを経験した私が、その見知らぬ土地で不意に出会った女の子にびんぼうぐさを手渡され、それを受け取った理由は、記憶の奥底にある「当時憧れていたお姉さんにびんぼうぐさをプレゼントした自分」と被ったからに他ならない。
つまり、同じ状況下で拒絶された過去の自分を受け入れたかったからという理由だったのだろう。
びんぼうぐさを受け取った私はそれを家に持ち帰り、庭の縁側に大事に隠した。何故か、見つかってはいけないような気がしたからだ。
その日から、その女の子はほぼ毎日私にびんぼうぐさを手渡すようになった。私は特に大きな反応もせず、淡々とそれを受け取り、縁側に隠すことを続けた。それを続けていくうちに、恐らくは『同じ状況下で拒絶された過去の自分を受け入れたかった』という理由はなくなり、そのこと自体を楽しみにするように気持ちが変化していた。
『ありがとう』
ある日コップの水が溢れるように、自然に声が出た。自分で自分の声を、遠くで聞いたような錯覚を覚えたようだった。
その女の子はニコッと笑った。初めて見た笑顔だったが、「もう一度見たい」と思わせるような会心の笑顔だった。『笑顔』と辞書を引いたら、彼女の顔が一番に出てくるであろうそれであった。
その日その瞬間から、私はその道で彼女からびんぼうぐさを受け取り、それと同時に素敵な笑顔を見せてもらうことが何よりの楽しみとなっていった。帰り道のその出来事のために、気の進まない学校へ行っていたといっても過言ではないくらいに。
ほぼ同時期に、学校生活も波に乗りかけて、友だちと呼べるクラスメイトも数人現れた。今にして思うと、「帰り道のお楽しみ」を身にまとった私の雰囲気が、他の誰かを受け入れる柔和なものに変わったことで、「転校生のラベル」が自然と剥がれつつあったのだと思う。
私にしてみたら、それは望ましい変化であった。
春から夏へ
女の子は「ゆぴちゃん」と名乗った。少なくとも、私にはそう聞こえた。ただ、「ゆぴちゃん」と呼ぶと例の会心の笑みが見られることから、「ゆぴちゃん」は「ゆぴちゃん」以外考えられないと私は思っていた。だから、『名乗った』と断言してなんの差し支えもないのだと思っていた。
ゆぴちゃんは私のことを「にんに」と呼んだ。恐らくはお兄さんという意味合いだろう。ゆぴちゃんは、年齢にしては口数が少なく、私が何か声をかけても不思議そうな顔をすることがほとんどだった。
(おはなしは、あんまりわかっていないのかもしれない)
よく見ると、いつも同じような服を着ていて、シャツは破れていてきれいとは言い難いものであった。幼稚園なのか、学校へ行っているのかもわからなかった。母親の「関わらないほうがいいわよ」という言葉が時折よぎったが、その真意は最後までわからないままだった。
そう、ゆぴちゃんの事に関しては、わからないことが多かった。何故毎日同じ道で立っているのか、なぜいつも一人なのか…。
とにかく、ゆぴちゃんと私は奇妙な友情めいたものを共有するようになった。ときに公園で、ときに道端で、会話にならないことがほとんどであったが、私はそれが日々の癒しのような時間となっていた。学校帰りに飛んで家に帰り、ゆぴちゃんを探し、砂場で遊んだり石を掘り返したり、空を見上げながら過ごした。
ふと思うと、ゆぴちゃんがびんぼうぐさを手にすることはもうなかった。びんぼうぐさは、ゆぴちゃんと私を繋ぐ役割を果たし、その役目を終えたのだろう。季節は、春から夏になっていた。
この時点の私に関して、私自身の自覚としてあったものは、『私は優しい人であろう』ということである。もう少しいうと、この『優しさ』ゆえに、ゆぴちゃんとの関係を持っていると自覚していたのだ。今にして思っても、子どもらしくない奇妙な感覚だと思う。そして、その『優しさ』は身勝手なもので、ややもすると『残酷さ』に変わってしまう類の『危険な棘をはらむ優しさ』だったのだ。
暑すぎる、夏
ひどく暑い日に、ゆぴちゃんは大粒の汗を垂らしながら、一生懸命私に何かを伝えようとしたことがあった。何度も聞き返し、やっと理解したのは、「私とおやつを一緒に食べたい」ということだった。私はなんて素敵な提案だろうと胸が弾んだ。それは、ゆぴちゃんも同じだったに違いない。
そして、その日はやってきた。
ゆぴちゃんは、例の会心の笑顔を惜しみなく私に向け、「買ってきたおやつを家に取りに帰る」という趣旨の事を告げ、その場を離れた。
私は、道端でゆぴちゃんを待った。それは何とも言えず幸せな時間のように思えた。
突然、自転車の急ブレーキの音がした。
ハッと我に返ると、そこには私のクラスメイトが自転車にまたがり私をじっと見ていた。そして「おーい、こんなところで何やってるんだ?空き地にみんないるから来いよ」と彼は威勢よく高らかに告げた。
私は口ごもった。ゆぴちゃんがおやつを取りに行っているのを待っていたからだ。間髪入れず、クラスメイトはさらに告げた。「ここでなにしてるんだよ?ドッチやろうぜ!」と。
私は咄嗟に理由を探した。この場から立ち去る理由を考えなければならない、そんな風に瞬時に解釈した。
(ゆぴちゃんと一緒にいるところを見られたら…悪い何かがあるかもしれない)
(そもそも、ゆぴちゃんとは少し遊んであげてただけなんだ)
(そうだ、待ってても戻ってこないゆぴちゃんが悪いんだ。しようがない)
私は思い切りよく言った。
「一緒に行く!」
精一杯の笑顔をクラスメイトに向けたつもりだったが、それは異質な笑顔だっただろう。
次の瞬間、急ぎ足で駆けてくる小さな足音が聴こえた。
ゆぴちゃんだ、と私はすぐに理解した。
意を決して振り返ると、間違いなくゆぴちゃんだった。手にはポテトチップの袋を大事そうに抱えている。もちろん、その顔は私の好きな会心の笑顔だった。
クラスメイトが私の異変を察知して尋ねた。
「なに、あいつのこと知ってるの?あいつさぁ…」
私は、一瞬母親の言葉を思い浮かべた。
「そんな子と関わらないほうがいいわよ」
(ゆぴちゃんと遊んでいると思われたら、クラスメイトと仲良くなれないかもしれない)
この判断の早さは、我ながら非常に恐ろしい。
私は迷わず言った。
「知らない。早く空き地行こう」
私はゆぴちゃんに背を向け、勢いよく走りだした。
クラスメイトと坂の途中まで下りた時、一度だけ振り返ってみた。ゆぴちゃんは、期待半分、不安半分の不思議そうな顔をして私を見ていた。
私は、ゆぴちゃんのことを裏切ったのだ。残酷な方法で、最もゆぴちゃんの気持ちを踏みにじる方法で。
それは、かつてお姉さんにあげたびんぼうぐさを、「きたないはなだ」と言った自分と同じだった。例え大事なものであっても、誰かの物差しで簡単に切り捨てられる残酷さを私は持っているのだ。
空き地でのドッチボールは、非常に充実していて楽しいものだった。私は、ゆぴちゃんのことはすっかり忘れていた。いや、思い出さないようにしていたのだろう。
その日、帰宅してシャワーを浴びた時、私は言いようのない恐怖を覚えた。ゆぴちゃんを裏切った後ろめたさや後悔が、それとは知らせず一気に襲ってきたようであった。文字通り、目の前が真っ暗になった経験は、後にも先にもそのときしかない。
びんぼうぐさをあなたに(再び)
この体験は、その後の私の人生の中で『予告せず登場する得体のしれない恐ろしいもの』という位置づけで、私のアイデンティティ(と言えるもの)を絶えず脅かし続けている。
陳腐なことを言うようだが、もし時間を戻せるなら…ひとつだけ過去を変えられるとしたら、暑い夏の日、あの場所へ時間を戻すだろう。
———————————————————————————————-
…
…
…
突然、自転車の急ブレーキの音がした。
ハッと我に返ると、そこには私のクラスメイトが自転車にまたがり私をじっと見ていた。そして「おーい、こんなところで何やってるんだ?空き地にみんないるから来いよ」と彼は威勢よく高らかに告げた。
私は口ごもった。ゆぴちゃんがおやつを取りに行っているのを待っていたからだ。間髪入れず、クラスメイトはさらに告げた。「ここでなにしてるんだよ?ドッチやろうぜ!」と。
…
…
…
「ごめん、先に約束があってさ。また今度遊ぼうぜ」
…
…
…