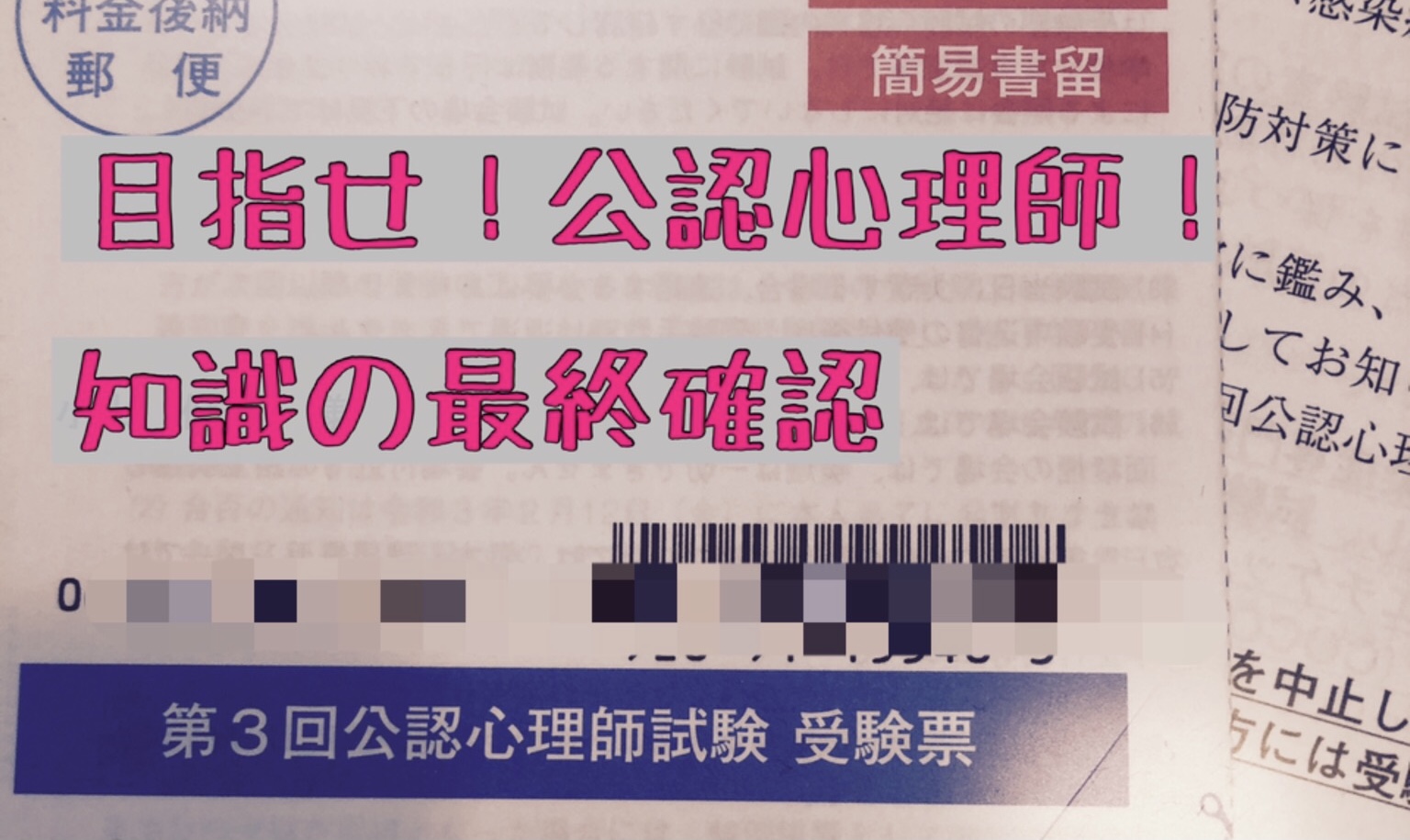第三回公認心理師国家試験に向けて、問われる可能性が高いと思われるポイントを抽出してみました。この記事は、以下の人に向けて書いています。
・公認心理師国家試験の勉強について、一通り重要用語などを学んでいること
・過去問は7~8割正答可能で、各選択肢の正誤とそれにまつわる解説などがおおよそ可能なこと
つまり、基礎的な知識持った上で、もう少し深めていくとより得点チャンスになるであろう事柄を、私基準でまとめてみたのが今回の記事です。
なお、単純な引っかけ問題や無意味に意地悪な問題、回りくどい表現や長い文章で誤答を誘うようなものは作りません。過去問を参考にする限り、本試験でもそんな問題はほとんどないと思われますので。
今まで得てきた知識の確認と、マニアックにならない程度により深い理解をするために、是非ご活用ください。一問一答式です!
|
設問
レット症候群(ICD)またはレット障害(DSM)は、女児のみに見られるとされている。
正解 ○
DSM-5では、レット障害は原因遺伝子が特定されたため自閉スペクトラム症・自閉症スぺクトラム障害から除外された。
正解 ○
まずは、DSM-5になってからの変更点として、レット障害について挙げてみました。他にも多くの疾患、障害等ありますが、単にカテゴリの変更ということではなく、「原因遺伝子の特定」ということから、レット障害に着目してみました。
DSM-5において、反社会性パーソナリティ障害は、18歳以前に素行症が見られ、20歳に達したことを条件に診断される。
正解 ×
→15歳以前に素行症が見られ、18歳に達したことを条件に診断されます。
DSM-5において、反応性アタッチメント障害は、生後5カ月に達していることが診断要件の一つとなっている。
正解 ×
→生後9カ月に達していることが診断要件に一つになっています。
DSM-5における「反社会性パーソナリティ障害」「反応性アタッチメント障害」の診断要件に関する年齢の基準についての問いです。紛らわしいので覚えてしまいましょう。
ADHD患者の10~20%は、うつ病を発症する可能性があるとされている。
正解 ○
ADHDの診断基準においては、不注意・多動性または衝動性の項目が6か月以上続くことが要件の一つとなっている。
正解 ○
問7
転導性の亢進は、ADHDに見られることはほとんどない。
正解 ×
→転導性の亢進とは、集中の困難さを表しています。
ADHDについての基本的な理解を経たうえで、上記の項目も押さえてしまいましょう。また、ここでは触れませんが、ADHDの治療薬に関しても基本的な知識として押さえておきたいところです。
限局性学習症は、養育環境などの影響も考えられるとされている。
正解 ×
→環境要因はないとされています。
アルツハイマー型認知症は、脳に異常なプリオンが蓄積することで発症する。
正解 ×
→アルツハイマー型認知症はβアミロイド蛋白が蓄積することが原因とされています。異常なプリオンが蓄積することで発症するのは、クロイツフェルト・ヤコブ病です。
DSM-5においては、認知症は神経認知障害という名称となった。
正解 ○
児童虐待防止法では、虐待通告受理後、原則「24時間以内に児童相談所や関係機関において、 直接子どもの様子を確認するなど安全確認を実施する」という規定がある。
正解 ×
→48時間以内です。
精神障害を知った者は、一般人であっても都道府県知事に対して指定医の診断や保護の措置の申請をすることができる。
正解 ○
プライミングのうち、ネガティブプライミングとは、ネガティブな感情を伴って想起されるものである。
正解 ×
→先行する刺激(プライマー)の処理によって、後続刺激(ターゲット)の処理が抑制される効果を、ネガティブプライミングといいます。引っかからないよう注意です。
プライミングは、長期記憶であり、宣言的記憶に分類されるものである。
正解 ×
→長期記憶の、非宣言的記憶に分類されています。
カプグラ症候群は、家族がそっくりの他人にすり替わったと訴える替え玉妄想であり、レビー小体型認知症で見られる症状である。
正解 ○
→幻視含めて、視覚の障害が関係すると考えられています。
フレゴリ症候群は、全くの他人を家族など身近な人だと錯覚してしまうことである。
正解 ○
→カプグラ、フレゴリ症候群両者の違いについて把握したいところです。
ストレスチェックは、メンタルヘルスの不調の未然防止を目的とし、結果は所管のハローワークへ報告する。
正解 ×
→「メンタルヘルスの不調の未然防止を目的」は合っています。結果の報告は労働基準監督署です。
労働安全衛生法は、使用者が安全配慮義務を負うことを定めている。
正解 ×
→労働契約法にて、安全配慮義務を定めています。間違いやすいです。
ベンダー・ゲシュタルト・テストの結果の評価に関して、5歳から10歳までは「パスカル・サッテル法」で行う。
正解 ×
→5歳から10歳までは「コピッツ法」です。11歳~成人は「パスカル・サッテル法」です。「コピッツ」という可愛い響きが年齢の若い人向きの評価方法です。
うつ病用ハミルトン評価尺度(ハミルトンうつ病評価尺度)は、うつ病の重症度を測ることはできるが、回復の度合いを測ることができない。
正解 ×
→うつ病用ハミルトン評価尺度(ハミルトンうつ病評価尺度)は、うつ病の回復の度合いも測ることができる検査です。
MAS(顕在性不安尺度)は、ミネソタ多面的人格目録(MMPI)の中の不安に関する質問50項目と、妥当性尺度のL尺度(虚偽尺度)から15項目、合計65項目から構成されている。
正解 ○
Vineland-II (適応行動尺度)では、構造化面接を行う。
正解 ×
→半構造化面接です。
Vineland-II (適応行動尺度)では、対象者の様子をよく知っている保護者や支援者に対して行われる。
正解 ○
頻出のVineland-II (適応行動尺度)です。よく押さえておきましょう!
K-ABCはカウフマンモデル(ルリア理論)とキャッテル-ホーン理論と言う二つの理論に基づいている。
正解 ○
K-ABCは子どもの認知能力を測定することができるが、学力については測定できない。
正解 ×
→学力の基礎となる習得度を測ることができます。つまり、心理学と教育的な視点を併せ持つ検査と言えます。
頻出のK-ABCです。年齢だけではなくこの辺りも押さえたいところです。
ビネー式知能検査で測定される知能は、Thurstone,L.L(サーストン)の多因子説に基づくものである。
正解 ×
→ビネー式知能検査で測定される知能は、Spearman,C.E(スピアマン)の提唱した2因子説の中の「一般因子」です。
DAM(グッドイナフ人物画知能検査)は、男性像のみを採点基準とするため、女性が描かれた場合は、対象者に男性を描いてもらうよう指示をする。
正解 ○
以上27問でした!
試験を直前に控えて
試験も2週間前に迫ってくると、できることも限られてくると思います。この時期に新しい知識や苦手な分野に敢えて挑戦するのは時間的にもったいないところですが、今ある知識から少し先の新しい知識を得ていくのは間違いではないでしょう。
今回挙げた問題は、基本的な知識から少し先の知識の獲得を意識して作問してみました。
特に、心理検査は非常に覚えにくく、統計と並んで苦手意識のある方が多いと思われます。しかし、ここからの出題は非常に多く、避けて通れないもの事実です。過去問に出ている検査については、開始年齢やその内容について把握することをお勧めします。その上で、検査の解釈などについて深掘りしない程度に把握すると得点源になると思っています。
最後まで気を抜かず、合格を勝ち取ろう!