はじめに
みなさんは、「KKD」という用語を聞いたことがあるでしょうか。私は、かつてある障害福祉の研修ではじめて耳にしたものですが、その後、この用語は一般的ではないものの、ビジネスに関する用語として語られることが多いことも知りました。
今回は、この「KKD」に焦点を当てて、既存の「KKDの支援」から脱却を図り、新しい「KKDの支援」を定義してみたいと思います。
どうぞ、気軽に読み進めてくださいね!
KKDの支援とは?
さて、その「KKD」とは、それぞれ頭文字を取って「勘と経験と度胸」のことを指しています。研修では、講師の先生は以下のようにお話しされました。
その話を聞いたのは、私が現場経験を5年積んだくらいの時期でした。そして、このお話は今に至るまで私の心に残っている話となっています。
「勘と経験と度胸の支援」とは、一体どのようなことでしょうか。思うに、文字通り「勘と経験と度胸」に頼って支援するスタイルだと思われます。そして、これは「指導と支援」の関係性の中で、どちらかというと「指導的なスタイル」として現れるようにも思います。
そして、このスタイルは以前の障害福祉サービスの分野では、よく見かける職員像だったようにも思います。それは、「前にも似たような利用者がいた」や「なんとかなる」「とりあえずやってみよう」などという言葉に現れていたことと思います。
私も、実際にある一人の利用者を見たときに、無意識にこれまで出会った誰かと結び付けている一面を否定できませんし、それがある程度一致したときに安心感を得て、支援に入ることもありました。まさに、経験から導かれる勘と、結果出力されたものが度胸と言えそうです。
しかし、これは否定ばかりもできません。障害福祉分野では、(もちろんどんな人間も一人一人異なるということは前提として)その本人が持つ個性、特性の幅が広く、ある障害名や症状だけでは、その人のほんの一部しか判断できないことがあるからです。
そのときに必要なものは、ある意味では勘と経験と度胸と言えてしまうかもしれません。
しかし、同時に危険な一面もあります。それは、勘と経験と度胸はあくまでその職員個人に内包しているものであることから、客観性を欠いてしまうこともあるからです。
ところが、客観性を欠くという一面もありつつ、そこにまた同時に存在するものは「その職員固有の関わり」でもあるのです。
さてさて、どうしたらいいでしょうか。
新訳、KKDの支援
私としては、「勘と経験と度胸」のみに頼ってしまう支援ではなく、その前提として、利用者理解には科学的な解明も必要なのではないかと思っています。ある場面では、データ化して行動特性を掴むことも必要かもしれません。勘ではなく、そのデータが実証したものを支援に落とし込んでいくのです。
そして、度胸ではなく、確かな材料を集めて、チームで支援に当たりたいと思います。それが基盤になったら、その職員固有の関わりも、もっと輝くのではないかと思います。
最後に、私の考えた新訳のKKDの支援をご紹介します。

今回は、KKDの支援についてお話ししました。何か、考えるきっかけになると嬉しいです。
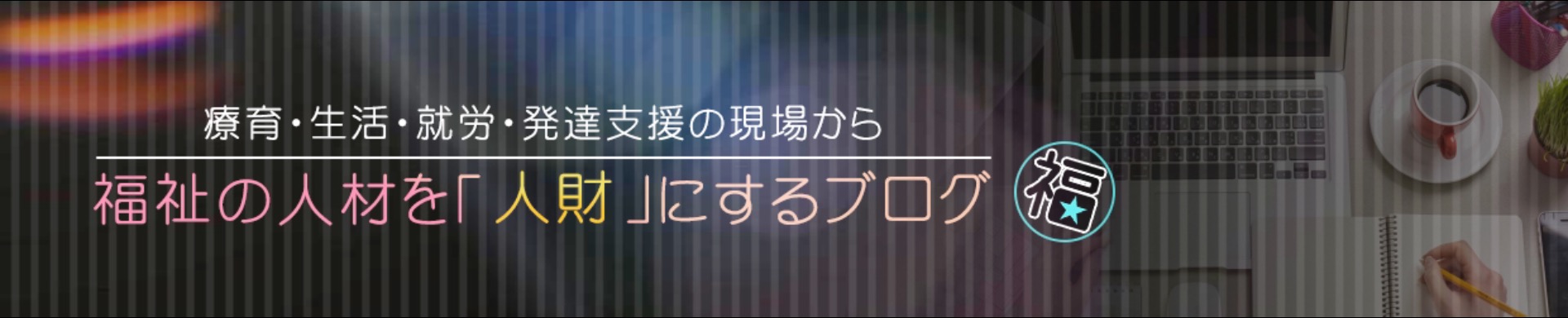
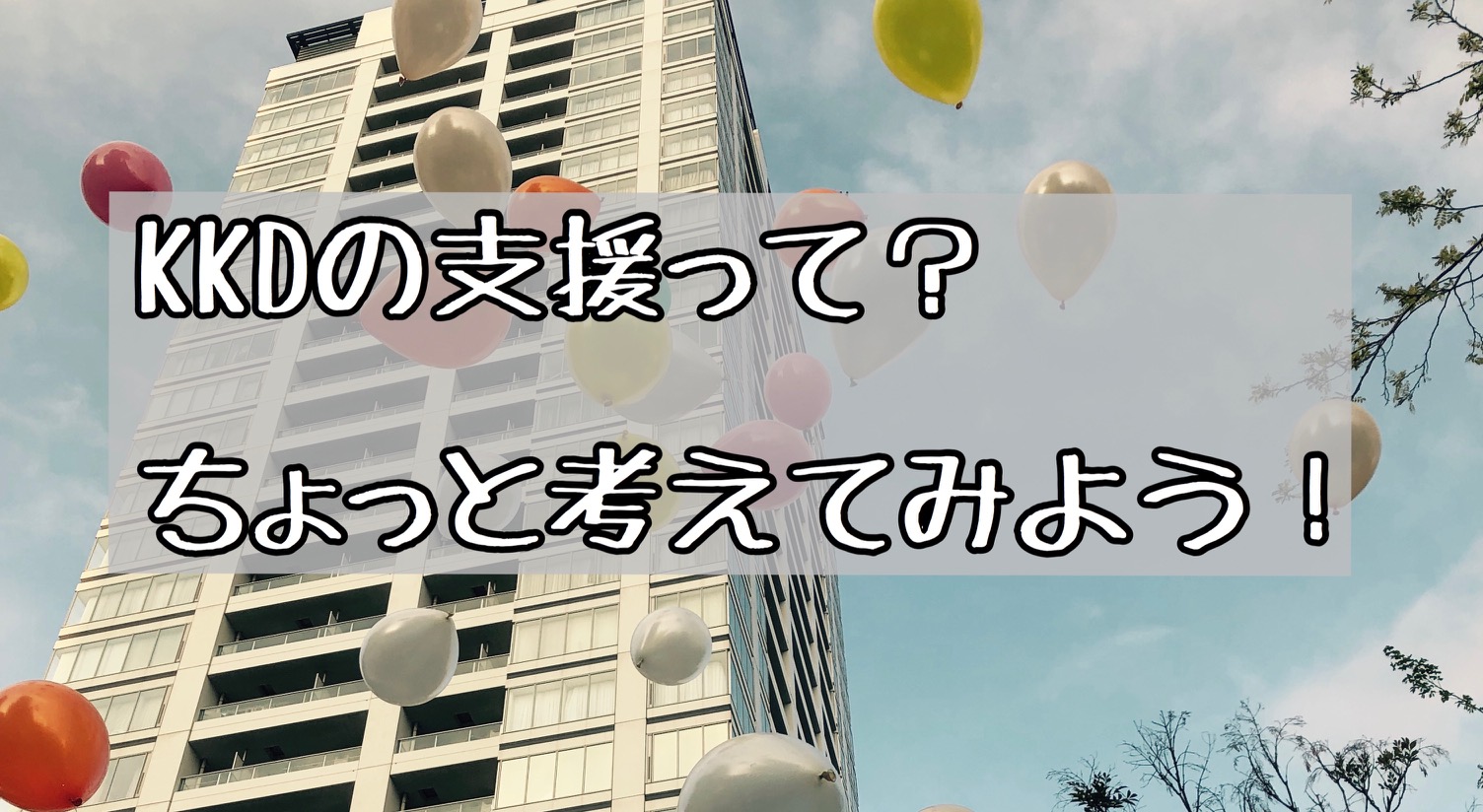
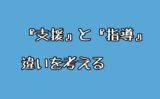

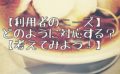
コメント