はじめに
今回は、『自然遊びと発達 ~五感を使った療育の実践~』というテーマで書いていきます。山の野良猫さん(@rururuahaaha)と一緒に、療育現場(児童発達支援や放課後等デイサービス)で使える遊びネタを紹介していきます。
山の野良猫さんとは、Twitterから以下のオープンチャットで知り合い、諸々活動をする仲間でもあります。
オープンチャット「学童・放デイ・保育園の状況改善を考えたい!」
本記事は、基本的には誰でも簡単にトライできる遊びを紹介していきます。そして、その中でどんな動きが発達に効果があるのか、解説していきたいと思います。
そんな疑問に少しでもお答えできるよう、現場目線で書いていきたいと思います。
子どもと自然遊び
さて、療育現場ではどんな遊び、活動を提供しているでしょうか。学習の支援や生活の支援をはじめ、パソコンなどを使った活動を提供しているところも多々あるかと思います。
もちろん、そういった活動も重要で発達支援に必要なものになりますが、ここでは『自然』をテーマにした活動を考えていきます。
見たり、聴いたり、触ったり…私たちはそれらの感覚から多くのものを得ています。子どもの頃にそれらの経験を積むことで、心身の発達はもちろん、感受性の豊かさという部分にも影響が多くあると考えられます。

さて、山の野良猫さんは自然遊びにどんなイメージがありますか?
森林浴や、海水浴と言う言葉がありますが、心身がリラックスできる場所といったイメージがあります。
また、安定の安心感があると共に、いつも新しい発見があります。「今日はどんなことがあるだろう。」と言う、ワクワク感もありますね♪
ところで、自然の中で遊ぶ経験をしていますか?
私も子どもの頃は毎日暗くなるまで近くの山や池、空き地で遊んだものです。(今もハイキングや磯遊びが大好きです❤️)
遊んでいながら子どもたちは様々な事を経験し、学んでいます。楽しい=遊びであって、学んでいるという意識はありません。
私も児童発達支援の保育士として、日々利用するお子さんの発達に関わっておりますが、自然遊びほど、子どもの発達を促すのに効果的な遊びはないと感じています。
その理由をいくつかご紹介したいと思います。
①感覚刺激に効果があります!
四季の移ろい、風の音、動植物など、見て聴いて触りながら五感を通じてたくさんの感覚刺激が入力できます。
デコボコ道や木登り、潜ったり跨いだり。基礎感覚(固有感覚やバランス感覚)、危険認知が遊びの中で養えます。
②自然の中には遊びのルールはありません!
誰がどんなふうに遊んでも大丈夫☆100人いれば100通りの遊びがあっていい。子どもたちが夢中になってしていることはだいたい「今、この子が育っているところ」(モンテッソーリでいう「敏感期」)です。それを満足するまで寄り添えばいいのです。
③発想を豊かにするとともに、社会性、協調性が育ちます。
一つの遊びが満足すると、また新しい遊びや刺激を子どもたちは求めます。遊びを自由に変えられる柔軟性があるのも自然遊びのいいところ♪
例えば、水たまり遊びでも年齢や発達、人数によって遊びはさまざまです。
感覚刺激→他者への気づき→共感→共有→役割分担へ。1人から2人へ、更に人数が増えると、それぞれの発想が混ざりさらに遊びを発展させていくことも可能です。
決まったルールがないということは、正解も間違いもないこと。「うまくいかなくってもまあ、いいか。今度はこうやってみよう」という発想の柔軟性も養われます。また、異年齢での関わりもしやすく、遊びの中で模倣や他者への親しみや思いやり、遊びの学びが深まっていきます。
④全ては自分で「体験する」からこそ、得られる「生きるための学び」
楽しかった、面白かった、ちょっぴり怖かったなど、実際に体験したことはなかなか忘れることはありません。インプット&アウトプットしやすいのも自然遊びの強みです。

ありがとうございます!自然と触れる重要さがよくわかりました!
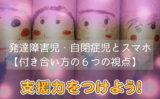

五感を使った遊びの実践

今回、山の野良猫さんは自然に触れるような遊びを、私は室内でも出来る、五感を使った遊びをご紹介します。まずは、私から!

『ホースを使った感覚遊び』
これは、至って簡単です。ホームセンターでホースを購入、それにビーズやパチンコ玉を入れて、輪っかにするだけです。輪っかする先は、ちぎれて中身が飛び出さないようにカラーテープなどでしっかり止めることが重要です。
制作のポイント
・透明のホースがあると、中身が見えて面白い
(カラフルなビーズや、スライムを入れると見た目が楽しい)
・いろんな大きさがあってもいい
(ホースの長さ50㎝くらいがちょうどいいです)
・鈴、お米などを入れて音が出るようにすると、楽器代わりにもなる
(両手でつかめるので、マラカス代わりになります)
遊び方と、発達支援のポイント
・その子どもの発達段階で、遊び方が変わってきます。例えば透明で見た目に惹かれるもの…これは見ても楽しめるもので、動かすたびに中身が変わるので、きっと手に取ってくるくる回してみたりするでしょう。
・ホースなので、掴んだ感触もいい感じです。ギュッと掴んだり、押してみたり。輪っかを二人で持って、引っ張り合ったりしても面白いです。
・ゲーム性を持たせることもできます。
例えば、輪投げにも用いることができます。輪っかをとじるときに使ったカラーテープの色別対抗にすると、色や数を知るきっかけにもなります。
立てて転がして、誰が遠くまで転がせるかというゲームもできます。重さや大きさでハンデも付けられます。
これらの遊び方から導くことができる発達支援は、まずは感覚を知ることです。掴む、振る、見るなどの刺激を受けることからはじまり、(透明のホースの場合は)動かすと中身の様子が変わることから、繰り返し遊び(循環反応)を引き出すことも可能です。
循環反応に関しては、ものの因果関係(こう動かしたら、そうなる)を学ぶきっかけにもなります。
次に、例えば輪投げなどに用いる場合は手と目の協応動作を引き出すこともできます。協応動作とは、この場合だと目と手が一緒に連動し、活躍するような運動のことです。
ホースを転がす遊びに関しては、バランスを取ることの大事さから、その因果関係も知るきっかけになるかもしれません。

それでは、次は山の野良猫さんがご紹介くださいます!
『草ソリ遊び』
草の生えている坂道を滑って遊びます。
【用意するもの】
ソリまたは開いた段ボール
体重の掛け方次第でスピード感を味わうことができます。
高いところから低いところへの動きを様々な姿勢で滑ることにより、姿勢保持や板書、目を上手く動かすことへ繋がっていきます。
不安が強いお子さんには、なだらかな坂から始めたり、大人と一緒に滑るのがオススメです。
また、坂道を登っていくのも、体の進行方向へ力を入れたり、ボディイメージへのアプローチにも効果的です。
遊び自体は単体での遊びですが、何人かで一緒に滑る、登るを繰り返していると、「ドキドキ、ハラハラ」「大変な坂を登って滑りきった」という、なんとも言えない達成感や一体感を生み出します☆
よそよそしかった関係が一気に仲間へ昇格させてしまう不思議な魔法を持っている遊びです(*^▽^*)
『道草遊び』
これは遊びとは言わないかもしれませんが。。。
散歩やお出かけの際、目的以外の場所に立ち寄ったり、子どもたちに行き先を決めてもらうのもいいですね♪
探検は子どもたちには魅惑のワードです。いくらあるいてもへっちゃら。かなりの運動量を歩くことができます。
あらゆるところを「道」にして歩きます。路側帯や、石垣、時には溝の中!いつのまにか足裏の刺激や平衡感覚に役立つ動きをしていることでしょう。段差のある場所を歩くのは、低緊張(姿勢保持が難しく、関節が軟らかい)お子さんにとっても無理なく運動ができます。
また、季節感を五感で感じ、身近な植物や生き物に触れられるのも道草ならでは。
小さな発見を友達と共感したり、大人に認めてもらえたりすると、自己肯定感も高まります。
小さなお子さんや発話に課題があるお子さんには一緒に見て触れて感じたものを言葉に表すと、言葉と実際の概念が育ちます。
標識を探したり「あそこを曲がると自動販売機があったね。」など、目印になるものを探しておき、確認しながら帰ると、認知機能、ワーキングメモリーにも効果があります。

うちのデイサービスでも、ウォーキングということで探検を取り入れています!近くに森があるので、みんなそこを歩くのが大好きです。春は気持ちの良い風を体で感じ、夏は葉っぱの緑を見て、秋は落ち葉を踏みしめ、冬は吐く息の白さを見て笑ったりします。
ただ歩くだけじゃない、小さな特別を見つけた時の喜びを噛みしめたいですね。
まとめ
子どもたちの遊びには便利なものや、危なくない配慮されたものが増え、「楽」や「快」を簡単に得られやすい遊びが増えています。
でもそれは裏を返すと、気に入らなければすぐにキレる、飽きやすいなど、自分本意に陥りやすい環境でもあります。自然遊びは思い通りにならない分、遊び込めた時の達成感や満足感は子どもにとってはかけがえのない宝物です。
なにより「生きる力」が身につく自然遊び。
ぜひ遊びに取り入れてみませんか♪
今回は、山の野良猫さんをお招きしてお話を伺いました。自然の中で楽しめる遊び、そして感覚を大事にした遊びの紹介をしながら、その発達への影響や効果を知ることができたと思います。
私も、大変勉強になりましたし、山の野良猫さんの視点が子どもの方を向いていることを感じられて、改めて原点を見つめなおす良いきっかけとなりました。ありがとうございました!
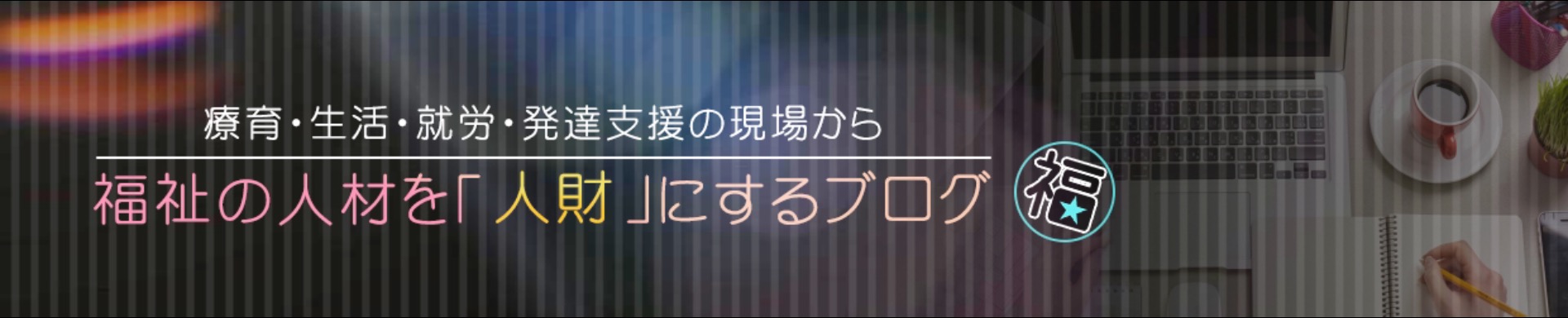
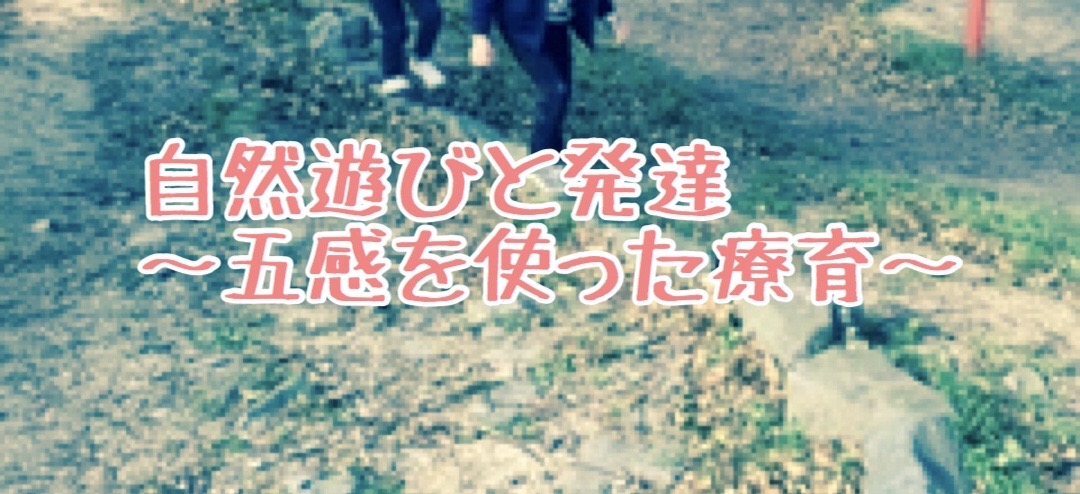



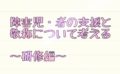

コメント